野中章弘×辺見庸×綿井健陽 対談(7)
作家 辺見庸とアジアプレス 野中章弘、綿井健陽が、
イラク戦争と報道、そして自衛隊派遣の論理を問う
(この対談は2003年12月27日に収録されたものです)
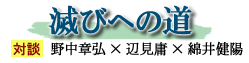

野中
辺見さんは以前、共同通信で働いておられて、企業の中のことはよくご存知だと思います。僕らは大学を出てからずっとフリーランスなんです。企業内の人達の感性がなぜ麻痺してしまうのかというのことを理解できないところがあるんですが、それについてはどう思われますか?
辺見
これについてはまだ思考過程で結論は出ていないんですが、僕はこう思うんですよ。一般にね、我々が世界というものを無理やりに解釈すると、僕は通信社で20代から横須賀の基地を取材したりしていました。はっと気がつくと、ああいう巨大な戦争装置、分刻みで、あるいは秒刻みでシステマティックに動いている。
そこに実は理性を感じているんだよね。いわば、現代の最先端の電子装置が使われていてそこには、何か人間の高度な理性が働いていると錯覚を起こしていましたね。
職場自体が、通信機器が革命的に発達するに従って、人間が思考すると言うよりは、ほぼ予測のとおりに順調に取材され、それが配信されるということがもっとも大事であるとされて、何がちゃんと伝えられているか、どういう視点が大事なのかはほとんど議論されない。
特に、会社全体がコンピューター化されてから完全にそうなったんですね。昔は、コンピューター化されていないですから、原稿用紙に書いて、ひどいときには議論の果てに「こんな原稿出していいのか」と殴り合いが始まるようなこともあったんです。
デスク全体が掴み合いになったりして。言ってみればそれも含めて人間的な会話があったんです。ところが、いま一番ないのは苦悩がないね。苦悩を対象化して話し合ってみることがない。急いで何時までに何行を何字出す、写真はどうするんだ、キャプションはどうするのか、と量をどんどん出してそれを差し替えていく。他社がこうなら、ウチも同じという発想しかなく、ウチはこういう取材だから独自にやろうという発想はないです。
そういうなかでシステマティックなものに極めて弱く、個別の目をもてないでいる。特にパレスチナは顕著ですよね。ハマスの兵士が瓦礫の中からゴム草履みたいなのを履いて出てくるのと、アメリカの空母から最新鋭の攻撃機が飛び立つのを見ていると、一方は理性が働き、一方は狂気しかないと思ってしまう。古い話をすると、ノスタルジーになってよくないけれど、ベトナム戦争時の石川文洋さんのように逆転した時代もあったと思うんです。
ホーチミンサンダルを履いて、飛んでくる飛行機を落とそうとする人間達に、僕らは共感をもったわけです。アメリカの攻撃機を一機撃墜する度に拍手したもんですよ。そういうのが今は編集局内でもないんだな。僕は湾岸戦争の時、共同通信で責任デスクをやっていたんですよ。
「一発くらいスカッドミサイル当たれよ」と思っていたけど、そういうこと言うと皆びっくりするんだね。そういうジョークすらなく、自分の思考様式が悪しき意味でグローバル化されていて、アメリカ的なものに大して無前提の理性を認めてしまっているんです。これは個々の人間だけじゃなく、マスメディア全体の傾向なんです。
NHKの手嶋ワシントン特派員はひどいね。ブッシュの演説の後で「感動的な演説でした」なんて言うのは、呆れてものも言えない。9.11からアフガンを経てイラクに至るまでのNHKの報道も、日本のマス・メディア史上に残る反省すべきものだと思いますね。ペンタゴンとの明らかな協力関係が出来ており、その中でブッシュのインタビューを勝ち取っていくプロセスは醜悪としか言いようがない。
次のページへ ...
















