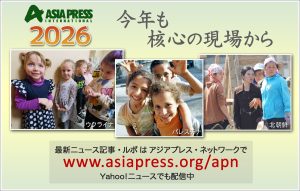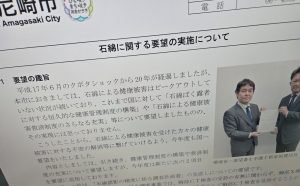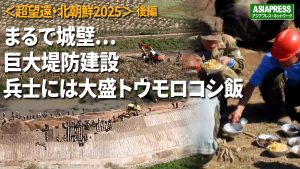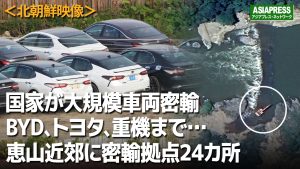北朝鮮当局は、コロナパンデミックが発生した2020年以後、閉鎖傾向を一層強めつつ、経済各部門の国家統制強化に突き進んだ。農業と食糧流通の分野でも大きな政策転換を試みている。これについては、改正された農業関連法を紹介しながら、農場現地の実態を交えて10回の連載で報告した。今回、あらためて「金正恩の農政改編」の核心を整理してみたい。(チョン・ソンジュン)
◆金正恩政権下で初の全面的な改編
2024年8月に韓国の国家情報院が公開した「北朝鮮法令集」によると、「農場法」、「農業法」、「糧政法」など、農業関連の法律が短期間に数回の改正を重ねていることが分かった。2020年2月から2021年11月の間に「農業法」は1回、「糧政法」は2回、そして「農場法」は4回も改正された。
それら法令に、咸鏡北道(ハムギョンブクト)と両江道(リャンガンド)に居住するアジアプレスの取材協力者3人が、この2年間に送ってきた農場の調査報告と照らし合わせると、金正恩政権の農政改編の狙いが浮かび上がってきた。
【全10回】<北朝鮮特集>金正恩氏が挑む農政改編とは何か(1) 農場から「協同」が消えた 農業関連法規を大幅見直し

◆農政改編4つ核心
金正恩政権の農政改編の核心は、次の4つに要約できる。
1. 農場の企業化
国家から土地と営農物資を与えられて、国家計画通りに糧穀を生産する単純な生産単位から、農場自らが計画し経営に責任を負う自律的な経営体に変化させようとしている。
「農場法」、「糧政法」などの改正を通じて、農場を「社会主義農業企業体」と定義し、農場の自律的生産、流通、価格決定権に対する法的根拠を付与した。
農場員である取材協力者からは、「農場が地主になりつつある」という言及があった。農場の裁量が拡大していることが、現地でも認識されていることが分かった。
2. 契約による買い取りと流通の構造改革
これまでは、農場で生産された食糧は、国家が国定価格で買い上げ、住民に供給する仕組みだった。農政改編によって、国家が買いあげる「義務収買」と、農場が各企業や工場と個別に結ぶ「契約による収買」に分化した。
これにより、農場と企業間の食糧取引は、国家計画の統制下にありつつも、実際の流通過程では農場と企業間の契約に基づく自律性が認められることとなった。
さらに協力者たちは、農場の余裕食糧を取引できる場として「営農物資交流所」が新設されたと伝えてきた。市場のような役割を担っているという。
3. インセンティブ制度の改善
分組を生産の基本単位とし、計画量(ノルマ)以上の追加生産分は、分組に属する農場員が分け合うことができる制度に移行中だ。
追加生産分に関しては、食糧として確保しておくことも、企業などと契約して売ることもできるようになり、農場員の自律性が拡大した。このような変化に伴い、農民に対する社会認識が、過去に比べて肯定的になったという言及もあった。これは、注目すべき点だろう。
それでも農民たちは、依然として新しい政策に対して半信半疑であり、新しいインセンティブ制度が定着するかどうかは、今秋の収穫を経てみないと分からないと見ているという。
4. 国家に頼ってこそ生存可能な構造へ
一連の農政改編は、一見、農場と農民の自律性を許容し、契約によって流通を活性化させる目論見が見えるのであるが、現在のところ、農場に対する国家統制はさらに強化されたようである。
例えば、「糧穀販売所」や「営農物資取引所」などの国営流通機関を通じた供給網が拡充・強化され、食糧の国家専売が現実化し、それ以外の食糧取引は徹底して取り締まりの対象になった。
また、農場員の主要な実質所得源だった「小土地」(不法個人耕作地)での耕作は全面禁止され、農民が国家に従属するしかない状況が造成されつつある。すなわち、農業分野における個人的な自立空間を徹底した遮断し、農民たちは、ただ国家に頼ってこそ生存が可能な構造を作ろうとしているのだ。