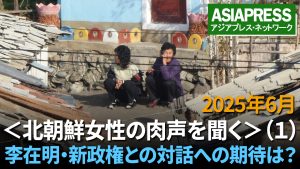◆事故に「構造的な問題」も
もう1つ気になるのは、なぜ今回の飛散事故を回避できなかったのかである。
カーテンウォール裏の吹き付け石綿除去だったうえ、非常に飛散しやすい青石綿を高濃度に含むことから難易度の高い除去工事だったことは間違いない。しかし適切に管理していれば、外部飛散することはない。
元請けは「強風の影響を受け養生が一部破損」と発表したが、外部養生の風雨対策など基本のはず。
念のため石綿除去の経験が長い技術者にも聞いたが、「建物外部の養生が風雨にさらされるのは誰にでもわかることですよね。雨が降ればあっという間に養生テープなんてはがれますし、強い風でも同様です。部分養生であっても外部養生であれば、風雨の対策をするのは当たり前です」と呆れていた。
その程度の対応すらできない技術力がないのか、あるいは手抜きをするずさんな工事だったということか。
ただし「最近では猛暑により養生テープが熱で溶けてしまって隔離養生が崩壊するということも起きています」というから、天候によっては同様の事態だったことも考えられる。その場合は養生の破損は1カ所だったとは考えにくい。
ちなみに作業開始前に県が養生検査をしているが、その際には問題はなかった。ただし屋外養生については、足場が一部足りておらず、危険性が高いため確認できなかったという。
県によれば、外部養生の風雨対策は作業の届け出に記載がなかったと認めるが、届け出の際に県が指導していたかははっきりしない。
そもそも作業開始前に負圧除じん装置の排気口をデジタル粉じん計で点検して数値を計測していたというから、石綿が漏れている状況だったことを確認できているとみられるが、なぜ装置の不具合解消などをしないまま作業を進めたのか。露骨な手抜き工事だったのか、石綿漏えいの可能性すら理解できないのか。あるいは何らか手抜き工事をせざるを得ない事情があるのか。
今回事業者が示した対策は養生確認と養生がはがれた場合にできるだけ早く見つけるというもので、風雨から養生を守るための抜本対策ではない。またカーテンウォールの石綿除去につきものである建物外部から除去が必要な箇所への対応をどうするのだろうか。
現状、事業者側の発表や県への取材した限りでは、こうした原因究明がきちんとできているとは言い難い。とりあえず現場の再点検だけ実施して工事を再開するようだが、本当に再発防止できるのか疑問である。
工事を発注した同商工会議所は5日、ウェブサイトで、解体工事現場からの石綿検出を認め謝罪。施工業者に「原因の早急な究明と再発防止」を指示し、作業では「安全、安心を最優先に確実に実行」するよう厳命したと発表。現状をどう見ているのか12日に連絡したが、担当者不在で話を聞くことができなかった。同日、除去作業を担った静勝にも何度か電話したが、「本日の業務は終了」との自動音声が流れるだけだった。お盆休暇なのだろう。
県の説明によれば、18日に行政立ち会いの下で改めて業者が養生検査し、19日に除去作業を再開。その際には県と業者のそれぞれが環境測定をする方針。
学校などにおける石綿除去や学校などに隣接する場合、とくに安全側に立った対応が求められるはずだ。まして一度石綿の飛散事故を起こしている以上、万全の対策が必要だ。すでに漏えいさせた現場で毎日空気環境測定をして安全確認をする程度は、本来最低限の対応のはずだが、県は指導しておらず、事業者の対応にも記載がない。
除去業者が委託する測定で石綿漏えい時などにデータ偽装で隠ぺいさせられるといった問題も起きており、単純に測定すればよいというわけではない。とはいえ、毎日測定するよう指導もなければ、自らそうした方針を表明することもないのはさすがに甘すぎではないか。周辺住民や学校側にどのように安全を示すつもりなのか。測定データなど、そのための最低限の裏付けのはずだが、法令通り今度は頑張りますというだけで本当に納得が得られるのだろうか。
今回は県による監視で石綿漏えいが発覚したわけだが、必ず県が測定するという仕組みにはなっていない。作業再開時に改めて県も測定するのはよいが、一度きりの対応で、その後は事業者任せである。
日本では石綿除去における第三者による監視・施工監理の仕組みが制度化されておらず、それが今回のような問題を引き起こす。今回も県の測定がなければ、漏えいが発覚しないままずっと垂れ流しだった可能性すらある。東京都や大阪・堺市などでそうした取り組みは始まってはいるが、あくまでごく一部の先進的な動きにとどまる。環境省中央環境審議会の答申でも第三者による監視の有効性は指摘されているのだが、現状では制度的な位置づけがないままだ。こうした構造的な問題の解消も必要だ。
【関連資料】旧小田原箱根商工会議所の解体におけるアスベスト飛散状況