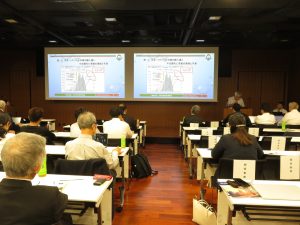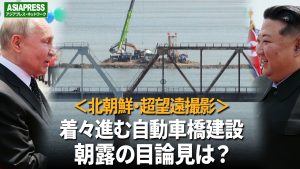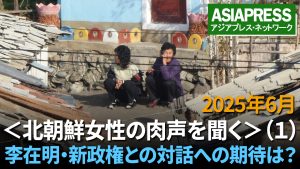アスベスト(石綿)による損害・被害は「法令遵守だけでは防げない」──。とくに建築物などから石綿を不適正に除去し、健康被害が発生した場合、所有者が責任を問われる可能性があるとして10月15日、どのような対策が必要なのかを解説するセミナーが東京都内で開催され、不動産業者や自治体、建設業者ら114人が参加した。(井部正之)

【関連資料】日本のアスベスト対策のおかしな部分をクイズで指摘。設問と解答、集計結果を再録
◆露出石綿で被害発生の責任は?
主催は建設資材のレンタル事業などを手がける日建リース工業ら6社で構成する「未来アスベスト被害ゼロプロジェクト」。後援は適正な石綿対策工事の実現に向けて施工管理技術者の育成などに取り組む日本石綿対策技術協会(ACA Japan)。
当日は同協会の姫野賢一郎理事長が「日本では石綿問題への関心が諸外国に比べて低く、法制度や対策も遅れています。日本の石綿工事の制度は『形』優先で飛散・ばく露防止に有効に機能しているか疑問。2021年に(建設現場で石綿ばく露した被害者らが国や建材メーカーを訴えた建設アスベスト訴訟の)最高裁判決で国が適切な規制を行わなかったことが違法と判断されたが、同じことが繰り返されないよう実効性のある取り組みが重要です」などと挨拶した。
セミナーでは、20年前から石綿被害者の救済訴訟に取り組むアスベスト訴訟関西弁護団事務局長の位田浩弁護士が「建物所有者と工事発注者のアスベスト被害に対する責任」との演題で、民法717条の工作物責任について解説した。
位田弁護士は鉄道高架下の建物を借りて文具店を営んでいた店主が倉庫として利用していた2階の壁に吹き付けられた石綿を吸って胸膜中皮腫(肺や心臓などの膜にできるがんで予後が非常に悪い)を発症し亡くなった事件を担当。
この件は、「工作物責任に基づいて、『通常有すべき安全性を欠いている』と判断された」と建物所有者の賠償が確定した2014年2月の(最高裁で差し戻し後の)大阪高裁判決について説明した。
しかも、その後同じ高架下の喫茶店やうどん屋でも同様の被害が発生していたことが相談で判明し、示談により建物所有者が賠償に応じたという。同じ高架下の吹き付け石綿でこれまでに計3人の中皮腫被害が出ていたことになる。
こうした経験から位田弁護士は、「建物改修で天井板をめくったところ、吹き付け石綿が露出して飛散するような状況があれば、『建物が通常有すべき安全性を欠いている』と評価され、工作物責任を問われることになる」と指摘した。