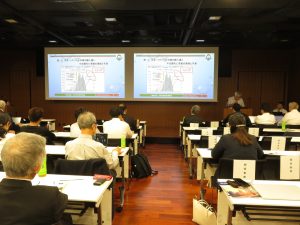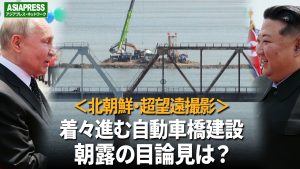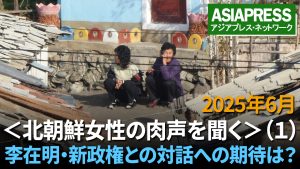◆除去業者のミスでも建物所有者に責任
続いて米国で石綿除去や施工管理に取り組むジャナス社シニア安全執行役のマイケル・シャープ氏が「予期せぬコストがアスベスト規制の執行と適正な管理実務を弱体化させる―米国の専門家が不思議に思う日本の規制と実務」について、日本の石綿対策を米国から見ていて感じることを講演した。
米国においては、学校で石綿含有建材の位置と状態を把握し、その情報を台帳として維持更新することが1986年にアメリカ環境保護庁(EPA)による石綿危害緊急対応法(Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA))で義務づけ。その影響により、ビルオーナーに対しても学校と同様の維持管理がされるようになっていった。
ビルオーナーが石綿の維持管理に注力しなくてはならない理由は、「管理主体規制(Controlling Entity Regulation)」との考え方が2000年前後に導入されたことだ。これにより、作業者や周辺住民に規制違反により石綿ばく露が生じる事態が起きた場合、規制違反を防止できた、または石綿ばく露・飛散を防止できた「可能性のある者」は誰であっても告発されることがあり得るとシャープ氏は解説する。
一方、日本においては、大規模なビルであっても大規模改修や解体の予算が決まり、発注が終わってから事前調査で初めて石綿の使用状況が明らかになって、発注者にとって想定外の費用や工期の遅れを招き、結果として、一部の石綿含有建材について「存在しない」ことにした違法な除去工事を選択せざるを得ない要因になるという。その原因は規制の不備だ。
石綿関連業務で厳格な免許・資格制度が存在せず、違法な調査・分析・工事をしても免許剥奪もない。しかも講習の内容がきちんと統一されておらず実地研修もないうえ、1度を修了すれば更新不要。不適正作業などの罰則は軽微(通常30~50万円)で適用はほとんどないありさまだ。
こういった現状に触れたうえで、「規制やその執行が不十分のため、コスト削減に手抜きや違法作業を行うことへの抑止力が弱い」「日本の法制度そのものが法令遵守を非常に難しくしているように思える」との見解を示す。