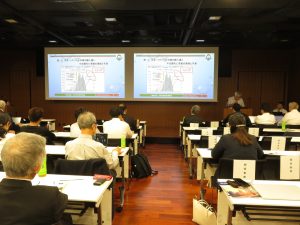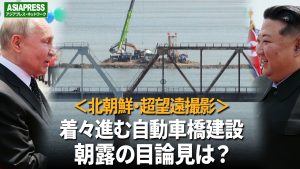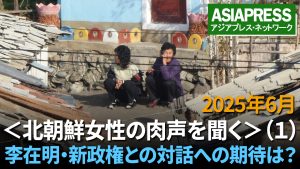◆石綿規制の抜本強化必要
解決策として、ビルオーナーなど発注者や元請け業者に長期的な責任を負わせる法制度や適正な作業手順と技術的対策を義務づける規制、免許・資格制度と罰則規制の実効性を高めて規制を機能させることがそれぞれ必要と訴える。さらに不適正施工による工作物責任を回避するため、米国で普及しているビルオーナーなど発注者が法令を上回る発注仕様を作成し、その実施を監視者を配置して管理する「対策工事管理(プロジェクト・マネジメント)」の導入を勧めた。
前出・日本石綿対策技術協会の理事でもある亀元宏宣事務局長は「デジタル粉じん計とスモークマシン:簡単だけどアスベスト工事を最も確実に監視する方法」として、実際の石綿除去作業で活用できる監視方法を解説した。
吹き付け石綿や石綿含有保温材などの除去などの作業では、作業区画の境界などで測定をして、石綿の漏えいが明らかになっても、試料採取から分析機関に持ち帰って結果を出すには通常数日から長い場合は1週間ほど要する。除去作業が終わってから漏えいが明らかになっても意味がない。
こうした除去作業では石綿の漏えいを防止するためにビニールシートを養生テープで固定してほぼ密閉状態にする「隔離養生」や、場内を減圧し石綿を高性能フィルターで取り除いて清浄な空気だけを外部に排出する「負圧除じん装置」を設置する。亀元事務局長らは粉じん濃度をほぼリアルタイムで計測できるデジタル粉じん計を使って、隔離養生の外側から直近の養生テープの目張り部分などや、きれいな空気だけが出てくるはずの同装置の排気口内を測定し、石綿作業の影響のない周辺濃度と比較して、それより高い場合は石綿漏えいの可能性があるとして現場改善をさせるのだという。
また作業場内でも測定し、作業時の石綿粉じんの発生抑制にも取り組む。
現場で測定結果を記録した野帳を示しながら亀元事務局長は、「何度も繰り返し測っているとこの場所はどういう濃度なのかわかってくる。常に測っているので、除去業者の作業者も濃度を気にするようになって、『いまどれくらい?』と聞きに来たりするようになる。そうすると1つのチームになって、石綿の漏えいや飛散をみんなが防止するよう動くようになってくる」と過去の事例から効果を話す。
日建リース工業事業開発部の大森道生部長は、「作業者を守る最前線『新しい防護服』」との演題で吹き付け石綿や石綿含有保温材など、高濃度の石綿ばく露があり得る除去などの作業で着用する防護服のあり方や今後販売開始する同社の防護服について説明した。
石綿除去などで使う防護服について、厚生労働省はマニュアルで「JIS(日本産業規格) T 8115:2015 化学防護服の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)又は同等品を使用する」と位置づけ。国内で流通しているのはその「適合品」がほとんどだ。