野中章弘×辺見庸×綿井健陽 対談(4)
作家 辺見庸とアジアプレス 野中章弘、綿井健陽が、
イラク戦争と報道、そして自衛隊派遣の論理を問う
(この対談は2003年12月27日に収録されたものです)
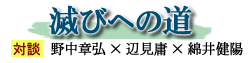

辺見 おっしゃる通りだと思います。果たしてこれだけのサイズの侵略攻撃のようなものを、サイズ通りに実像を伝えることが今のマスメディアの機能でできるのか、疑問があるのです。
我々は戦争というと19世紀から第2次大戦、近々ではボスニア、湾岸戦争のようなものを考え、ビジュアル的にハードウェアをイメージするんです。でも戦闘というのは実はハードウェアだけじゃなく、ソフトが大きな役割を占めていると思います。
例えばサダム・フセインの銅像を引き倒されるところが、メディアイベント的には勝利の瞬間になっていて、世界の集合的な記憶、つまりパブリックメモリーというのはあそこで形成されるんです。
そうすると、ああいう情報の製造のされ方が戦争そのものだと思うわけです。戦争とはメディアであるという仮説を僕は立てているんです。人間の拡張がメディアであるとすれば、戦争とはまさにそうじゃないか。
ところが、旧来型というと反発を受けそうですが、日本のジャーナリズム論だと、一人一人のリポーターやディレクターの心根が正しければ正しいことができる、と言われていますが、僕はそうじゃないと思っています。実際マスメディアに集まる人間は極端な悪党だけではなく、どちらかというと善意な人間が多いんです。その善意の人間が集合化するととんでもない嘘の報道になってしまうのは何故なのか。
「個々の合理的な判断というのは全体としてはとんでもないミスリーディングな部分がある」とサミュエルソンという経済学者が言っており、合成の誤謬という言い方をするわけだけど、まさに戦争報道はそうだと思うんです。個々が見てきたもの、カメラマンが映したとことは断片的には事実でしょう。でも、それを切ったり貼ったりしているうちに戦争像全体としては変なことになってしまう。
綿井さんがおっしゃったように、子ども達の反応はそこで当初から刷り込まれている。教員や親、社会もそうですよ。「どっちも悪い」という言い方ですよね。アメリカ自体もそうだと思うんですよ。アメフト場5面くらいを真空のようにしたディージーカッター爆弾で殺された死体は目が飛び出ていて、臓器も口から噴き出すくらいひどくて、作った科学者も死体を見たくないというくらいひどいものなんです。
それはアフガンのトラボラ地区で落とされており、村民の証言もあるんです。ところが、現代社会の両義的なところで、その爆弾を作っている人達は敬虔なクリスチャンでミサを欠かさず、エコロジストで煙草も浮気もしない人達なんです。そういう人間達によって戦争の残虐な側面が善意で作られていくという両義性が見えないと駄目だと思うんです。今のマスメディアではそういう視点は出し得ないと思うんです。
次のページへ ...
















