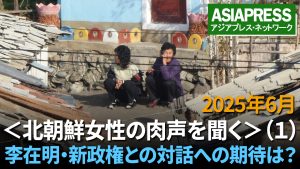◆国家の責任を免除させる「戦争被害受忍論」
「政府は長射程ミサイルの配備は抑止力を高めると主張します。しかし、抑止力が万能ではなく、抑止が破れて戦争が起きることも想定しているのは明らかです。ところが、台湾有事から中国との戦争が起きた場合の日本側の被害の予想、民間人にどれくらいの犠牲者が出るかなどについて、政府はまったく説明しようとしません」
そう訴えるのは、湯布院駐屯地へのミサイル配備に反対し、日出生台演習場や十文字原演習場での日米共同演習・訓練などの監視活動を続ける市民団体「ローカルネット大分・日出生台」事務局長の浦田龍次さん(62)だ。

「説明すると、民間人の戦争被害のリスクが明らかになり、軍拡路線に反対する声が高まる
と政府は考えて、説明を避けているのではないでしょうか」と、浦田さんは推察し、そのような政府の姿勢の背後に、「戦争被害受忍論」があるのではないかと述べる。
「戦争被害受忍論」とは、「戦争という非常事態において国民は被害を等しく耐え忍ばなければならない」という政府側の主張で、アジア・太平洋戦争中の空襲被害者など民間人の戦争被害に関する国家補償の要求を、政府が拒む際に唱えてきたものだ。

救済を望む空襲被害者らが国家補償を求めて起こした訴訟でも、国側(政府)は「戦争被害受忍論」を持ち出し、裁判所もそれを認めて訴えを退けたりしている。
「戦争被害受忍論」。それは民間人の戦争被害を「やむをえない犠牲」と位置づけて、戦争を起こした国家の責任を免除させるもので、政府にとっては実に都合のいい考え方である。(つづく 14 >>)
吉田敏浩(よしだ・としひろ)1957年、大分県出身。ジャーナリスト。著書に『ルポ・軍事優先社会』(岩波新書)、『「日米合同委員会」の研究』(創元社)『昭和史からの警鐘』(毎日新聞出版)など。