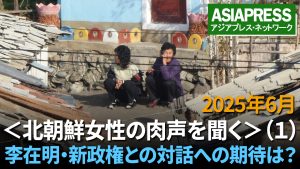◆「戦争被害受忍論」という非情な棄民政策
つまり戦争が起きてみないと、軍事目標かどうか判断できないというのだ。しかし、戦争で弾薬庫が軍事目標として攻撃されるのはわかりきったことだ。住民が犠牲になり、人命が失われてから、やはり軍事目標だったと判断しても手遅れで、とりかえしがつかない。

弾薬庫は軍用車両などとは違い、固定施設で動かせない。住民の安全に配慮するなら、そもそも人口密集地やその近辺に設けてはならないのは当然ではないか。
「ジュネーブ諸条約第1追加議定書に関する国際赤十字の解説書にも、『平時から弾薬庫など恒久的な軍事施設を人口密集地やその近辺に建てるべきではない』ことが書かれています。政府が進める弾薬庫増設は、国際人道法の『軍民分離原則』に反しており、ただちに中止すべきです」と、「市民の会」事務局次長で元大分大学教授の合田公計[ごうだきみかず]さん(73)は力説する。

防衛省と外務省の回答から浮かび上がるのは、住民が戦禍に巻き込まれても仕方ないという「やむをえない犠牲論」である。住民の犠牲も計算に入れたうえでの戦略、軍事優先の非情な棄民政策にほかならない。
それは「戦争という非常事態において国民は被害を等しく耐え忍ばなければならない」という「戦争被害受忍論」に通じる。「やむをえない犠牲」である以上、等しく受忍しなければならないというわけだ。

実際、戦争に備える有事法制のひとつ国民保護法をはじめ、現行の各種法令においても、戦争による生命・身体・財産などの被害に対する国家補償の制度はない。「戦争被害受忍論」の強い影響力がみられる。(つづく 15 >>)
吉田敏浩(よしだ・としひろ)1957年、大分県出身。ジャーナリスト。著書に『ルポ・軍事優先社会』(岩波新書)、『「日米合同委員会」の研究』(創元社)『昭和史からの警鐘』(毎日新聞出版)など。