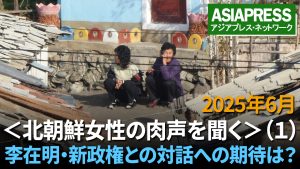「戦争という非常事態において国民は被害を等しく耐え忍ばなければならない」という「戦争被害受忍論」。政府はこれを念頭に置いて、戦争が起きた場合の住民の犠牲も想定ずみ、織り込みずみで、長射程ミサイルの配備や弾薬庫の建設、民間空港・港湾の軍事利用など、大軍拡と戦争準備を進めているのではないか。(吉田敏浩/写真はすべて筆者撮影)
◆弾薬庫建設で軍事の力学が暮らしの場に踏み込んでくる
大型弾薬庫を増設中の陸上自衛隊(以下、陸自)大分分屯地(通称、敷戸弾薬庫)。敷戸団地など住宅密集地の真ん中に残る丘陵地にあり、近隣の5つの小学校区内だけでも約2万世帯4万人が暮らす。

有事に弾薬庫が攻撃されれば、周辺住民にも戦禍が及ぶのはまちがいない。増設予定9棟のうち1棟目の着工直前の2023年11月2日に開かれた、防衛省九州防衛局による住民説明会では、そうした不安と不満の声が参加者の間から口々に発せられた。

「約130人が参加して、保管する弾薬の種類や量、爆発事故や有事に標的となる危険性などを質問しましたが、防衛省側は『防衛上の機密で答えられない』、『十分な安全対策をとる』と繰り返すだけで、私たちの不安に応えようとはしませんでした。しかも、そのときは弾薬庫2棟を増設ということでしたが、それから間もなく、2024年度予算案でさらに7棟もの増設計画が明らかになりました。住民説明会ではまったく出なかった話で、だまし討ちです」
そう防衛省・自衛隊の強引さに憤りを表すのは、地元の敷戸北町の元自治会長で、弾薬庫増設に反対する住民などが結成した「大分敷戸ミサイル弾薬庫問題を考える市民の会」(以下「市民の会」)の共同代表を務める、元会社員の宮成昭裕さん(75)だ。

冷酷なまでの軍事の力学が、有無を言わせず暮らしの場に踏み込んできている。防衛・軍事について国民・市民は口出しをするなと言わんばかりの防衛省の対応である。その背後には、『防衛・安全保障は国の専管事項』という政府の持論があると思われる。
次のページ:◆戦争加害の行為をも正当化する「戦争被害受忍論」…↓