日本での西サハラに関する発言や記述には間違いが多い。政府機関や関係者が率先して誤った情報を発信し続けているケースもある。西サハラの実情を知らなければ、意図的に流される誤情報に気付きようがない状況が生じている。(岩崎有一/写真はすべて筆者撮影)
西サハラのタブー化に加担する日本外交の異様(1) JICAも大企業も 教科書には載せられない破廉恥な地図
◆そもそも成り立たないクイズ問題
「アフリカのモーリタニアとモロッコから日本が輸入する約6〜7割を占める海産物はなんでしょう。」
2024年9月28日と29日、グローバルフェスタJAPAN2024が東京・新宿で開催された。このクイズは、同フェスタの公式ウェブサイト「国際協力を学ぼう!参加しよう! Let’s ODA Quiz」に出てくる1問だ。
このグローバルフェスタの主催は同フェスタ実行委員会。共催は外務省と国際協力機構(JICA)、国際協力NGOセンター(JANIC)によるもの。全4問のうちの3番目が冒頭の質問だ。答えはタコ。だが、モロッコでは輸出するほどの量のタコは獲れない。
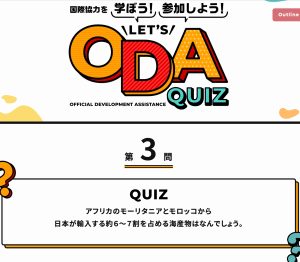

◆JICAは高度な政治判断まで?

2021年2月15日、JICAのウェブサイトに「日本の食卓を支えるモロッコに最新海洋・漁業調査船が就航」と題するページが投稿された。岡山県の造船所で建造されたこの調査船は、海洋と水産資源の調査をするものだ。同ページには「日本に輸入されるタコの約2~3割がモロッコ産で、マグロやイカなどおなじみの水産物もモロッコから多く輸入されています」と記されている。JICAはXの公式アカウントで、「1万キロ以上離れたモロッコの人と、同じタコを食べながら。」と投稿した。
モロッコから輸出されるタコのほとんどは西サハラの海でとれたものであり、モンゴウイカも同様だ。西サハラの港では、タコはTAKO、モンゴウイカはMONGOと記されるほど、これら西サハラ産水産物と日本との関わりは深く長い。また、日本の漁船がモロッコに操業料を支払って西サハラの海域でマグロ漁を行う実態もある。
日本はモロッコによる西サハラの領有を認めていない。しかし、JICAの言説では、西サハラでとれる水産物はモロッコのものだということになる。


◆ポリサリオが会議場に入り込む? 事実にそぐわない元大使らの論考
外務省在職経験者を会員とする一般社団法人霞関会のウェブサイトに、元駐モロッコ大使花谷卓治氏と前駐モロッコ大使倉光秀彰氏による西サハラの論考が掲載されている。両論考とも、著しく正確さを欠く記述が延々と続く。
“8月24-25日、都内で開かれたアフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合にポリサリオ戦線の代表が入り込み”(花谷氏)
“なぜ彼らがTICAD会合に参加しようとしてモロッコと衝突を繰り返すのか”(同上)
“その(サハラーウィ難民キャンプの)正確な人口さえ把握できていない”(倉光氏)
“民族的にモロッコ人・モーリタニア人とサハラウィは同根であり、歴史的、宗教的、文化的な差異もほとんどない。”(同上)
“ラバトにおいて観察する限り、ポリサリオ戦線には国家を統治できるような能力は不十分であり、また組織自体の持続可能性も乏しいという印象”(同上)

昨年東京で持たれたTICAD9閣僚会合には西サハラ住民が建国したサハラ・アラブ民主共和国(SADR)の外相とAU担当大使が参加したが、合法的に入国し正式な手順で参加しており、“入り込んで”はいない。また、SADRがモロッコと衝突したことはなく、過去の暴力沙汰はすべてモロッコが自ら起こしたことだ。
アルジェリアのチンドゥーフにあるサハラーウィ難民キャンプでは、赤新月社が世界食糧計画(WFP)などからの食糧を世帯ごとに計画的に分配している。同赤新月社代表によると、2023年2月時点でサハラーウィ難民キャンプの人口は18万人を超えた。人口がわからなければ食糧の計画的分配など不可能だ。

モロッコのベルベルとアラブ、西サハラのサハラーウィ、モーリタニアのムーアなど、それぞれの民族に“差異もほとんどない”ことはなく、文化的な違いが明確に存在する。
1973年に発足した民族解放組織のポリサリオ戦線と同戦線が樹立したSADRには国家に必要なあらゆる組織が備わっており、西サハラ域内と難民キャンプ、周辺国に暮らすサハラーウィの統率と連携は保ち続けられている。半世紀以上続く解放戦線を「統治能力が不十分で持続可能性に乏しい」とするには無理がある。

次のページ:◆“衆目の一致”、“西サハラは瓶のふた”……論理の飛躍の数々…↓












![<北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡 <北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡](https://www.asiapress.org/apn/wp-content/uploads/2010/12/201010070000000view.jpg)










