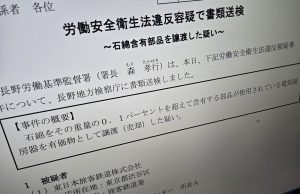◆政界の危機感はすでに国民の常識
1月半ばを過ぎ、断続的だが通信が開通すると、国内のニュースメディアも活動を再開させた。保守・改革いずれのメディアも、抗議デモについて連日、政治家の発言やアナリストの論評、独自の論説を組んだ。
今回の抗議デモの直接の原因を危機的な経済状況にあるとし、それをもたらしたものが政府の「過激主義」であるとする考えは、改革派だけでなく保守派の論調の中にも見られる。
背景として、イランには特定の基幹産業に対する補助金や、重要産業の原材料の輸入に格安な為替レートを割り当てる優遇為替レートの存在があり、このシステムはコネや贈収賄を蔓延させ、一部の関係者に莫大な利益をもたらしてきた。
こうした優遇為替レートや補助金につぎ込まれていたのは、この国の「不労所得」である石油収入に他ならないが、その貴重な財源を、核開発やミサイル開発、近隣諸国の軍事組織への資金援助に惜しげもなく投入し、その結果、経済制裁を招き、石油収入を減少させたばかりか軍事攻撃までをももたらした。そこには、軌道修正を拒み、欧米諸国との敵対姿勢を貫き、諸外国との緊張緩和のチャンスをことごとく潰してきた「過激主義」が政府の中にあり、それこそが国民を疲弊させ、今回、国を窮地に陥れたという理論である。
しかしこのような考えはほとんどの国民にとって周知の事実であり、友人も怒りを込めて言う。
「経済制裁されて生活が苦しくなるならウラン濃縮は二の次でいい。多くの国民にはウラン濃縮の見返りなどないのだから」
イランでは近年、2017年、2019年、2022年と抗議デモが頻発しているが、これまでのデモと大きく異なる点の一つは、わずか半年前に自国を空爆したアメリカの大統領や、そこに住む元皇太子の呼びかけに多くの人が反応を示したことだ。そこには、現体制以外ならどのような選択肢でも構わないという絶望が見て取れる。
あまりにも多くの命が失われた今回のデモで、絶望と敵意は増幅されただろう。平穏を取り戻した町の水面下で、喪に服す市民の心の声は、どこまで政権中枢に届いているのだろうか。(つづく)
***********************************
大村一朗(おおむら いちろう・アジアプレス)
1970年生まれ。静岡県出身。2012年春まで首都テヘランに滞在。イラン国営放送ラジオ日本語課に勤める傍ら、フリーのジャーナリストとしてイランの生活、文化など広く取材。2009年には大統領選挙後の抗議デモに足しげく通い、騒擾下のテヘランの実情を内部から伝えた。 現在、奈良在住。著書 『シルクロード路上の900日』(めこん)、共著 『21世紀の紛争』(岩崎書店)