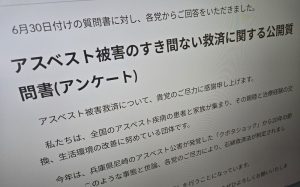イスラエルのガザ侵攻から1年と9か月が経つ。パレスチナのガザ地区住民のおよそ5万9千人以上が犠牲になり、9割が家を失った。ガザは今や見る影もなく、家々は瓦礫の山となった。イスラエルは3月2日よりガザ住民への水や食糧の配給を止め、アメリカとイスラエルが支援する「ガザ人道財団(GHF)」が配給を行っているが、連日配給を待つ人々が銃撃を受けるなどして死傷者が増え続けている。一方、イスラエル軍は避難命令を出しつつ、避難地域でも空爆を強めている。昨年の11月から「ガザ女子学生日記」を書いて日本で発信しているサバラさん(仮名23歳)からインターネットで現状報告が入った。(古居みずえ)
ガザは今…古居みずえが現地女性に聞く(1) 「目覚めは戦闘機とヘリの飛行音と空爆」「悲しみと死は至る所にあります」

◆危険戦闘地域に
ガザ南部に住んできたサバラさんが、避難生活から自分の家に戻ってきたのは、2024年11月だった。粉々になった壁、割れた窓、方々から漂う死の臭いと埃にもかかわらず、月日を経て、破壊された自分の家を受け入れ始めていた。家を元の姿に戻すことに希望を託した。小さな鉢に植物を植え、毛布を敷き、心の中でつぶやいた。「もしかしたら、ここが再び故郷になるかもしれない」と。
しかし2025年6月2日、サバラさんの住む地域が「危険戦闘地域」に指定された。再び避難しなくてはならないと家族に告げられ、出発の準備を始めた。サバラさんは手が震え、心臓がドキドキ鳴ったという。部屋中のもの全部持っていきたかった。でも人生を一つのバックに詰め込むことは無理だった。
◆幼馴染バジルの死

6月3日サバラさんは胸が張り裂けるような悲しみで目が覚めた。静かな朝だった。しかし父親の叫び声が刃のように静寂を切り裂いた。
「バジルが殺された!」
バジルさんはサバラさんにとってただのいとこではなく、幼馴染で、本当の姉弟のようだったという。
サバラさんと家族は急いで服を着て、遺体安置所へ急いだ。その場で働いていた男性が「バジルさんはアメリカの救援トラックから援助物資を受け取ろうとしていたところ、イスラエル軍の狙撃兵に撃たれた」と話してくれたという。
イスラエルは3月2日にガザ住民への水や食糧の配給を止めた。5月末から国連などの国際機関に代わり、イスラエルとアメリカの主導による「ガザ人道財団(GHF)」が食糧配給を始めていた。しかし、配給所付近で行列を作って並んでいる人たちに向けて連日のようにイスラエル軍などによる発砲が行われている。それでも空腹を抱えたガザ住民は食ベ物を求めて、配給に並ぶしか方法がない。バジルさんもその一人だったとサバラさんは語る。
「バジルは2023年10月に父親を亡くして以来、一家の大黒柱となっていました。まだ少年だったバジルでしたが、一夜にして大人になることを余儀なくされたのです。飢え、恐怖、そして生きるための重荷を背負い、パンを探しに出かけ……そして血まみれの死体となって帰ってきたのです」
サバラさんによれば、バジルさんには母親と、6人の姉妹がいた。彼は彼らにとって唯一の希望であり、戦闘の苦しみと人生の厳しさを和らげてくれる存在だったという。

◆再び家からテント生活へ
6月5日
サバラさんは家族とともに家を出た。
「家を出るということは、単に場所から場所へと移動するということではありません。慣れ親しんだすべてを根こそぎにされ、記憶が粉々に砕かれ、魂を追放されることなのです」
それはサバラさんにとって人生最悪の日だった。2度目の故郷からの避難だった。
「私に残っていたのは、バッグとテント、薄れゆく記憶、そして形も約束もない未来だけでした。これは単なる戦争の残酷さではありません…これは沈黙を選んだ世界の裏切りなのです」
6月6日
親族の家で一日だけすごした後、テントを張れる場所を求めてさまよった。ようやく見つけたわずかな区画に荷物を置き、テントを張った。
「これから寒い夜や灼熱の太陽から身を守ってくれない布切れの下で暮らすことになるのでしょうか? このもろい世界の片隅で、残りの人生を過ごすことになるのでしょうか?」
テント暮らしは、最もつらい。プライバシーも安らぎもない。些細なことでも苦労の種となる。サバラさんにとって避難という苦しみが再び始まった。
「私は家、魂、そしてこれまでのすべてを捨てた日でした。私の人生の意味が奪われ、避難という苦しみの章が始まりました。避難とは、ただある場所から別の場所へ移動することではありません……避難は死に似ています。ただし、墓のない、ゆっくりとした死です」
◆死を覚悟した夜

6月8日
サバラさんはこれまでも何度か死を覚悟するような場面に遭遇していた。テント生活になってまだ数日しかたっていない夜のことだった。サバラさんと家族が、長く疲れ果てた一日を終えて一息つこうとしていたときだった。
「空が深く不自然な赤色に輝き始めました。上空から奇妙な音が響きわたりました。イスラエルの軍用機から私たちの近くに照明弾が投下され、夜はもはや暗くはありませんでした。まぶしいほどの明るい光がすべてのものを白日の下にさらし、影さえも奪いました」
「戦車の音は大きくなり、ロケット弾の轟音が空を満たし、恐怖が私たちの骨の髄まで突き刺さりました。私たちはどこへ行けばいいのか、何をすればいいのかわかりませんでした。唯一の避難場所であるテントは、銃弾や砲火から私たちを守ることはできないと思いました。私はこれがこの世で最後の夜になるかもしれないと、心から感じました」
サバラさんによると、パニックの声が至る所で響き渡った。人々は叫び、走り、逃げようとしていた。恐怖に打ちひしがれ、身動きが取れなくなった人たちもいたという。
「私たちはテントの中で地面に伏せ、息をするのも、動くのも怖くなり、流れ弾に当たらないことを祈っていました。避難生活を送っていても、すべてを失った後でも、私たちは依然として死に追われています。でも私たちは死にませんでした。どういうわけか、私たちは生き延びたのです」